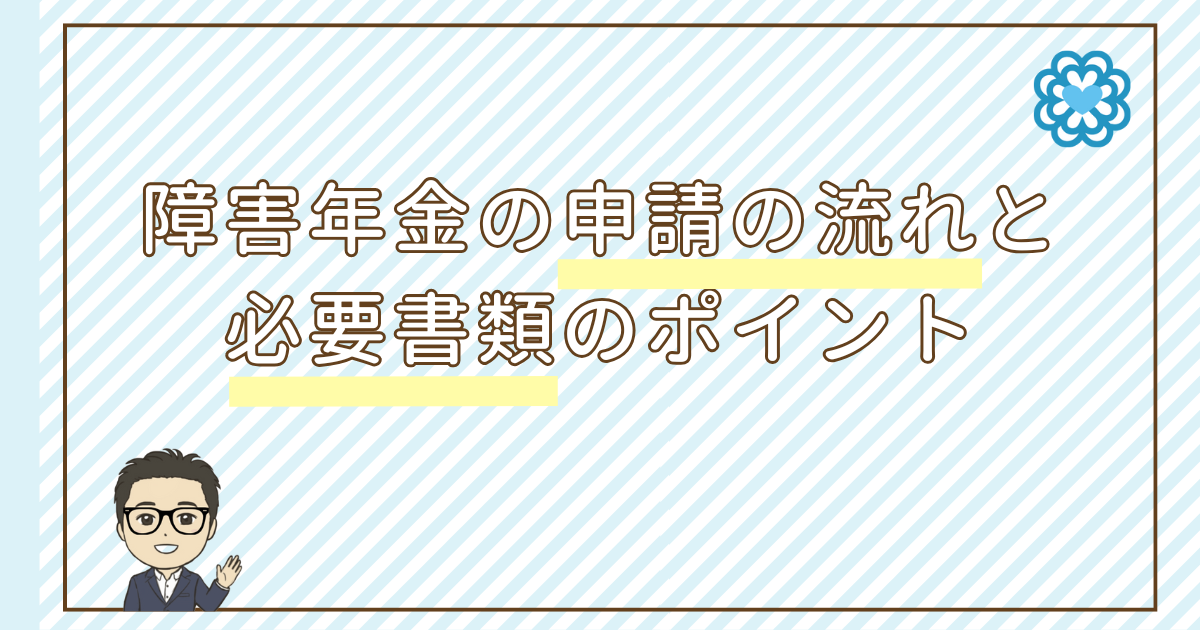江東区で障害年金の申請サポートをしている「心と福祉とお金に強い社労士」西川です。
この記事では、障害年金を申請する際の具体的な流れを、実際の事例をもとに詳しく解説します。どのような書類が必要で、どのように準備を進めるかを分かりやすく説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
モデルケースと必要書類
モデルケース
- 氏 名:江東太郎さん(46歳・うつ病)
- 家族構成:妻(44歳)、子(17歳、高校生)
- 診療記録:
- 初 診 日:令和2年 2月1日(A病院)
- 障害認定日:令和3年 8月1日(B病院・等級非該当)
- 現 在:令和6年12月1日(B病院・等級2級相当)
江東太郎さんは、障害認定日には障害等級に該当していませんでしたが、現在は障害状態が悪化して2級相当となったため、このケースでは事後重症請求が適用されます。事後重症請求では、請求日の翌月分から障害年金が支給されます。
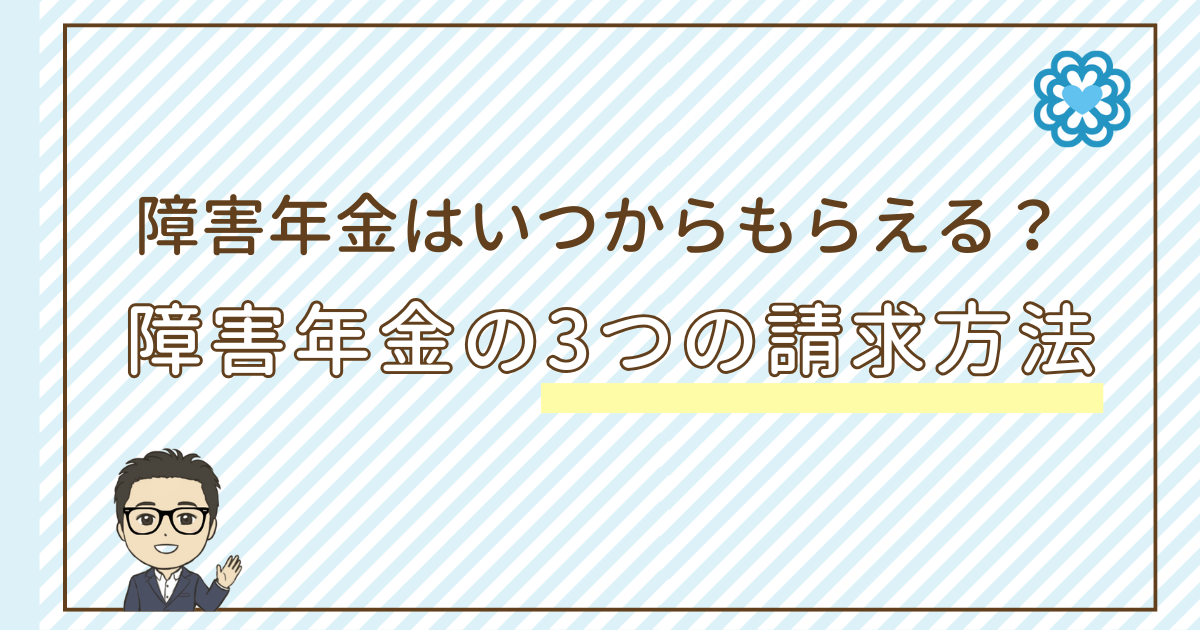
必要書類(提出する書類)
| 書類名 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 基礎年金番号の確認 | |
| 年金請求書 | 障害年金の申請書 | 障害基礎年金用・障害厚生年金用あり(年金事務所でもらえる) |
| ※住民票(世帯全員分) | 配偶者・子の加算確認 | 請求日前1か月以内のもの(※請求者の基礎年金番号がマイナンバーと情報連携できている場合は不要) |
| ※配偶者の所得証明書 | 配偶者加算の確認 | 年収850万円以下が条件(※年金請求書に配偶者のマイナンバーを記載した場合は不要) |
| 子の学生証 | 子の加算の確認(高校在学の場合) | 学生証のコピーか在学証明書 義務教育中の子は不要 |
| 受診状況等証明書 | 初診日の証明 | A病院で取得 |
| 精神の障害用診断書 | 障害状態の確認 | B病院で取得。請求前3か月以内の日付が必要 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 詳細な病状や日常生活の記録 | 診断書を補足する資料 |
| 年金生活者支援給付金請求書 | 障害基礎年金1・2級に該当する人が追加で支給される | |
| 預金通帳の写し | 振込先口座の確認 |
請求の流れ
- 障害年金の受給要件を満たしているか確認する
- 年金事務所で障害年金申請に必要な書類をもらう
- 初診の医療機関(A病院)に受診状況等証明書をもらう
- 現在の医療機関(B病院)に診断書をもらう
- 病歴・就労状況等申立書を記入する
- 各種提出書類(住民票等)を取り寄せる
- 年金請求書を記入する
- 年金事務所または市区町村役場の年金窓口に年金請求書一式を提出
- 結果が郵送される
- 障害年金が送金される
1.障害年金の受給要件を満たしているか確認する
この3つの要件を満たしているかどうかを確認します。
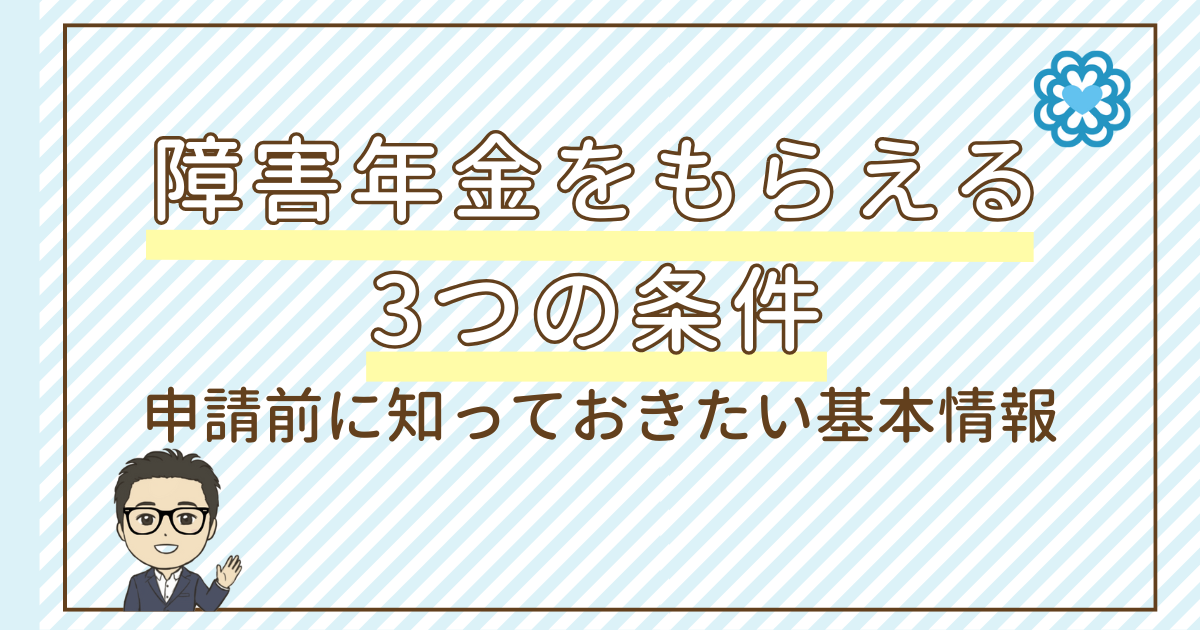
まずは初診日の特定です。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に診療を受けた日のことです。
初診日が分からないと、障害年金の受給要件を満たせるかどうかを確認することができません。
| 初診日確定 | 初診日に加入している年金が分かる(障害基礎年金か障害厚生年金か) |
| 保険料納付要件を満たすことができるか分かる | |
| 障害認定日が分かり、そのときの障害状態によって、認定日請求か、事後重症請求かが分かる |
2.年金事務所で障害年金申請に必要な書類をもらう
年金事務所に行って(要予約・年金手帳持参)、障害年金の申請に必要な書類をもらいます。
また、年金事務所で、初診日を伝え、保険料納付要件を満たしているかどうかを確認します。
3.初診の医療機関(A病院)に受診状況等証明書をもらう
初診日の証明は、初診の医療機関が作成した受診状況等証明書(初診日を証明する書類)となります。
受診状況等証明書の様式は、年金事務所からもらうか、日本年金機構のホームページから入手します。
それを医療機関へ渡して、書いてもらいます。
初診の医療機関と、診断書を作成する医療機関が同じ場合は、受診状況等証明書は不要です。
この記事の事例では、初診の医療機関(A病院)と診断書を書いてもらう医療機関(B病院)が異なるため、受診状況等証明書が必要になります。
受診状況等証明書が取れない場合は、他の手段で初診日を証明することができます。
4.現在の医療機関(B病院)に診断書をもらう
障害年金申請用の診断書の種類は8種類あります。
- 目の診断用
- 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
- 血液・造血器・その他の障害用
この事例では、うつ病のため、精神の障害用の診断書を使用します。
請求日以前3か月以内に受診した時点の障害状態が書かれた診断書が必要です。
診断書を受け取ったら、開封して自身で中身に間違いや不備がないかチェックする必要があります。
5.病歴・就労状況等申立書を記入する
発病から現在までのストーリーを記載します。
3~5年程度を区切りにして記載します。
病院に受診していない期間も、病状や病院に行かなかった理由等を書く必要があります。
6.各種提出書類(住民票等)を取り寄せる
世帯全員の記載がある住民票が必要ですが、請求者の基礎年金番号がマイナンバーと情報連携できている場合は不要です。
マイナンバー連携ができていない場合は、住民票の提出が必要ですが、住民票を取るときは、「世帯全員分」「続柄あり」「マイナンバー記載なし」で発行してください。
住民票はマイナンバーカードがあれば、コンビニで取得できます。
事後重症請求の場合は、請求日前1か月以内の日付の住民票が必要です。
医師の診断書ができてから、入手しましょう。
加算対象となる配偶者や子がいる場合は、世帯全員の記載と続柄が書いてある住民票等(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票の記載事項証明書)が必要ですが、年金請求書にマイナンバーを記入することで添付を省略できます。
今回のケースは、高校生の子がいるため、高校に在学していることの証明(学生証のコピーか在学証明書)が必要になります。
7.年金請求書を記入する
年金請求書は年金事務所で入手します。
初診日に、国民年金加入か、厚生年金加入かによって、年金の請求書が分かれます。
8.年金事務所または市区町村役場の年金窓口に請求書を提出
すべての必要書類を揃えて、年金事務所または市区町村役場の年金窓口に、年金請求書一式を提出します。
障害厚生年金、もしくは初診日が国民年金第3号被保険者期間中(例:会社員の妻で専業主婦)の障害基礎年金を請求する場合は、年金事務所に書類を提出します。
初診日が第3号被保険者以外の国民年金で、障害基礎年金を請求する場合は、市区町村役場の年金窓口に提出します。但し、この場合も年金事務所に提出しても大丈夫です。
9.結果が郵送される
年金請求書一式を提出すると、審査が始まります。
審査が通り、支給が決定すると、自宅に年金証書と決定通知書が届きます。
審査に通らなかった場合は、不支給決定通知書が届きます。
申請してから結果が郵送されるまでの期間は、3~4か月です。
10.障害年金が送金される
支給が決定して、年金証書等が自宅に届いてから、指定の銀行口座に障害年金が振り込まれるまで、約50日かかります。
つまり、申請から障害年金が初めて振り込まれるまで、5~6か月かかります。
申請の準備期間を含めて計算すると、申請の準備から振込までの期間(申請準備を含めて送金までトータルの期間)は、6~9か月が目安です。
社労士に申請を依頼するメリットとデメリット
メリット
社労士に申請を依頼するメリットは大きく2つあります。
- 申請の大部分を任せられるため、労力が大きく楽になること
- 申請の不備・問題を最小限にできること
ここでいう申請の不備・問題とは、書き間違いや書類不足だけではなく、申請者の障害状態と障害等級の不一致を最小限にするという意味で書きました。
たとえば、本当は障害等級1級の状態なのに、診断書がきちんと反映されていなくて不支給や2級になったり、病歴・就労状況等申立書の記入に間違ったことや誤解を招くようなことを書いたことで不支給になったり、障害等級2級となるリスクを最小限にするという意味です。
デメリット
社労士に申請を依頼するデメリットは、費用の発生です。
- 費用はおおよそ年金の2か月分+消費税かかる(遡及請求の場合はもっとかかる)
費用は事務所によって異なりますが、事後重症請求の場合、年金の2か月分+消費税が報酬の相場です。
成功報酬制がほとんどなので、年金受給が決定し、初回振込されて、報酬を支払います。
申請のためにしっかり時間を割いて勉強できる人は、ぜひご自身で申請してください。
診断書の見方や、病歴・就労状況等申立書の書き方は、押さえておきましょう。
入門書を見てもさっぱり分からず、申請が難しいと感じられた方は、専門の社労士に申請を依頼することを検討してください。