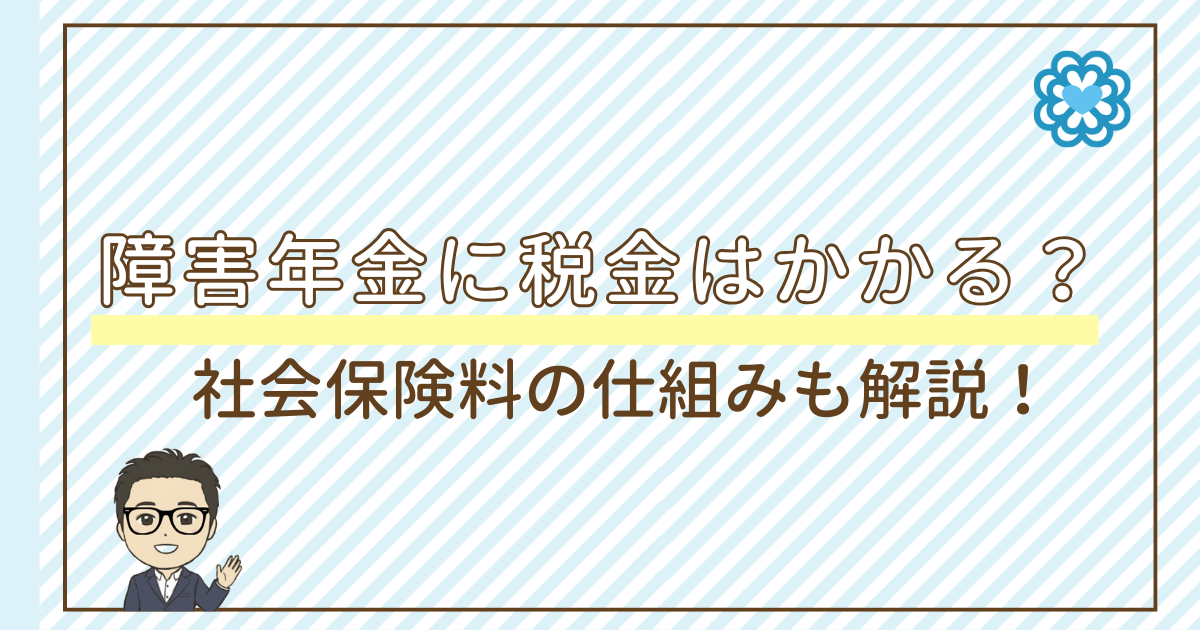江東区で障害年金の申請サポートをしている「心と福祉とお金に強い社労士」西川です。
会社員や公務員の場合、給与からは税金や社会保険料が差し引かれて支給されます。
それでは、障害年金の場合はどうでしょうか?
今回の記事では、障害年金の受給時に関係する税金や社会保険料について、ポイントを分かりやすく解説します。
障害年金と税金
私たちが原則65歳で受け取れる老齢年金は、課税対象です。
つまり、所得税や住民税がかかります。
一方、障害年金は、非課税です。
つまり、障害年金に対しては、所得税や住民税はかかりません。
但し、障害年金以外の所得がある場合(給与など)は、その所得に対する所得税や住民税は発生します。
- 老齢年金には所得税や住民税がかかる
- 障害年金には所得税や住民税がかからない
- 障害年金以外の所得(給与など)には課税される
確定申告の必要性
障害年金は非課税のため、障害年金のみもらっている人は確定申告をする必要はありません。
確定申告が必要な人は、障害年金と会社からの給料のほかに、年間20万円以上の収入がある方です。
確定申告が必要になるケースは以下の場合です。
- 障害年金以外に、年間20万円以上の副収入がある
- 給与所得があり、年末調整が行われていない
社会保険の扱い
収入が障害年金のみの人を想定します。
その場合、所得税・住民税はゼロですが、年金保険料、健康保険料は支払う必要があります。
就労していない場合は、国民年金保険料、国民健康保険料を支払う必要があります。
また、40歳になった月から介護保険料の支払いも発生します。
国民年金免除の選択肢
障害年金1級もしくは2級の場合、申請することで国民年金保険料の支払いを全額免除することができます(法定免除と呼びます)。
免除期間中の保険料は、老齢基礎年金の受給資格としてカウントされるだけでなく、支払わなくても老齢基礎年金の半額が受け取れる仕組みになっています。
たとえば、20歳から法定免除の場合、原則65歳で受け取れる老齢基礎年金の額は、満額の半額が支給されることになります。
但し、障害基礎年金をもらう権利がある場合は、65歳以上でも障害基礎年金をもらい続ければよいため、特に問題はありません。
国民年金保険料を支払うか免除にするか問題
障害年金の有効期間について、永久認定と有期認定があり、永久認定の場合は、更新不要で生涯に渡って障害年金を受け取ることができます。
たとえば、手足を切断した場合や、失明した場合など、今後障害の状態が改善される見込みがない場合は永久認定となります。
うつ病などの場合は、今後障害の状態が変わる可能性があるため、障害年金は1年~5年間の有効期間となります。
この場合、障害年金をもらい続けるには、診断書を提出し、障害年金の更新をする必要があります。
永久認定の場合、国民年金は免除一択ですが、有期認定の場合、国民年金を免除にするか、保険料を支払うかは悩むところです。
障害年金の受給が一時的だと思われる場合で、国民年金保険料を支払う余裕がある場合は、将来、老齢基礎年金をもらうときに備えて、国民年金保険料を支払う(任意納付・追納)ことが望ましいでしょう。
健康保険料のポイント
国民健康保険については、障害年金をもらっている人も支払う必要があります。
但し、障害年金の場合、給与所得などに比べて、国民年金保険料は安くなります。
国民年金保険料は、均等割・平等割、所得割・資産割の合計額ですが、所得割を計算する際の所得に障害年金は含まれません。
障害年金と給与収入等の合計が年間180万円未満の場合は、親や配偶者などの健康保険の扶養に入ることができます。
その場合、国民年金第3号被保険者となり、国民健康保険料を支払う必要はなくなります。
親や配偶者の健康保険の扶養に入る条件は以下の通りです。
- 生計を一にしている
- 本人(扶養に入る人)が75歳未満
- 障害年金と給与などの収入を合わせた総収入が180万円未満
まとめ
障害年金の税金や社会保険料について、今回は以下のように解説しました:
- 障害年金は非課税なので、所得税・住民税はかからない
- 国民年金保険料は法定免除が可能(1級・2級対象)
- 障害年金受給が一時的と見込まれる場合は、国民年金保険料を納付することが望ましい
- 国民健康保険料は支払う必要があるが、扶養に入ることができれば支払わなくてよい
障害年金の申請や受給にお困りの方は、ぜひ専門家にご相談ください。