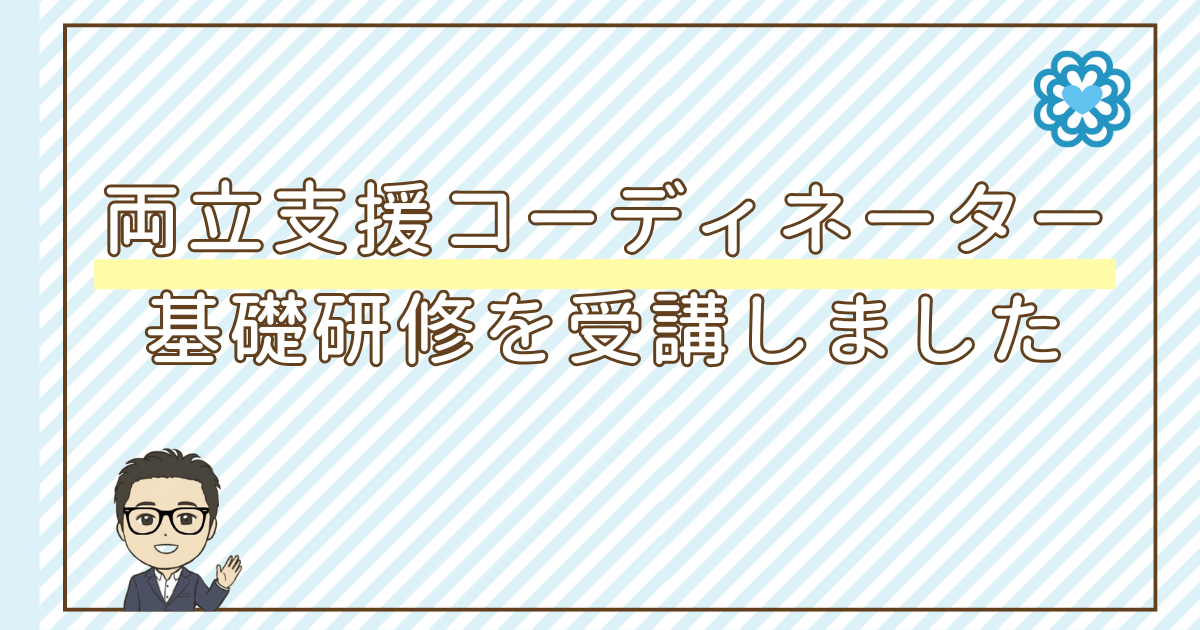江東区で障害年金の申請サポートをしている「心と福祉とお金に強い社労士」西川です。
この度、両立支援コーディネーター基礎研修を受講したので、受講のきっかけや内容などを書いていきたいと思います。
両立支援コーディネーターとは
両立支援コーディネーターとは、労働者が治療と仕事の両立に向けて、支援対象者、主治医、会社・産業医などのコミュニケーションが円滑に行われるよう支援する者で、行政法人労働者健康安全機構が養成しています。
たとえば、働いている人が、がんになって療養が必要になったとします。
以前は、会社を辞めて療養に専念する人が多かったと思います。
しかし、働き手(患者)の側からすると、会社を辞めることなく、仕事と療養を両立させたいというニーズを持っている人は多いのではないでしょうか。
受講のきっかけ
私が働いている職場で、病気になった人がいました。
その同僚は、働き続けることを希望していたのですが、休暇日数の制限のため、退職せざるを得ませんでした。
その同僚と同じ立場の私としては、複雑なネガティブの感情がありました。
それからしばらく期間が経ちましたが、社会保険労務士になってから、他の社会保険労務士のブログを見て両立支援コーディネーターの存在を知りました。
障害年金の申請を支援する立場として、医療機関や会社をコーディネートする知識やスキルが学べるのは自身のスキルアップにもってこいですし、なにより、病気で退職した同僚のようなことが起こらないように必要な知識を学びたいと思い、受講しました。
両立支援コーディネーターが求められる背景
労働者が病気になっても働き続けられる社会というのは、成熟した社会だと思います。
政府として、よりよい社会を目指していくことはもちろん背景としてあるのですが、治療と仕事の両立が大きく求められる背景としては、少子高齢化による労働者の減少が大きいです。
今後、労働者がどんどん少なくなること、労働者の平均年齢が上がってくることが分かっています。
高齢になるほど、病気になる割合は増えるため、治療をしながら働く人が多くなります。
また、医療の進歩によって、がん患者の5年生存率は年々上昇しています。
労働者を雇う会社側としても、今後は働き手の確保がどんどん難しくなってくる中、治療と労働の両立できる体制を整備することが求められます。
厚生労働省は、「治療と仕事の両立が当たり前の社会に!」のスローガンを掲げ、両立支援体制の社会的整備を推進しています。
何をコーディネートするのか
両立支援コーディネーターは、大きく3者をコーディネートします。
- 労働者(患者)・家族
- 主治医・医療関係者・病院
- 会社・産業医
主体(支援対象)は、労働者(患者)です。
| 労働者 (受診) | → ← | 医療機関 (病状や治療計画を伝える) |
| 労働者 (医療機関からの情報を伝える) | → ← | 会社 (配置転換・環境整備) |
労働者が、医療機関に受診し、主治医が本人や家族に病状や治療計画を伝えます。
労働者が、企業に医療機関からの情報を伝え、会社が配置転換や環境整備などの対応をします。
それがスムーズに行けば、コーディネーターは不要ですが、なかなか簡単にはいきません。
そこで、両立支援コーディネーターが、医療機関と会社との間で、情報を共有し、円滑に進むような支援を行います。
具体的には次のような役割があると思います。
- 労働者に、役立つ情報(傷病手当金や高額療養費制度など)を提供する
- 労働者に寄り添って、心理的に支えていく
- 労働者が抱えている課題を一緒に整理する
- 課題の優先順位を決める手助けをする
- 課題の解決を一緒に考える
- 労働者に、ニーズに合った専門家を紹介する
- 医療機関との連携・調整をする(勤務情報を主治医に提供するサポートなど)
- 会社との連携・調整をする
- 会社が作成する「両立支援プラン」の作成が適切かつスムーズに行くようなサポートをする
両立支援プランとは
事業者は、労働者の状態を考慮して、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュールについてまとめた計画を作成することが望ましいとされています。
この計画が両立支援プランです。
両立支援プランは会社側が作成するものですが、会社の産業医や保健師、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー・看護師等や、産業保健総合支援センター、保健所等の保健師や社会保険労務士等の支援を受けることが考えられます。
産業保健総合支援センターでは、治療中の労働者が就労を継続するために、両立支援促進員等の専門スタッフが、両立支援に関する取り組みの普及啓発や、事業場の支援などを行っています。
両立支援コーディネーターの担い手
両立支援コーディネーターは、それ単独での職業として想定されているものではなく、従来の関係者が両立支援コーディネーターとして支援することが想定されています。
たとえば、次のような人です。
- 会社の人事労務担当者
- 会社の産業保健スタッフ
- 医療機関の医療ソーシャルワーカー
- 看護師
- 支援機関の専門家(社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントなど)
両立支援コーディネーターに求められる知識と期待されること
両立支援コーディネーターに求められる知識と期待される役割は次の通りです。
- 医療の知識
- 心理学の知識
- 労働関係法令の知識
- 労務管理に関する知識
- コミュニケーションスキル
- 患者、主治医、会社などのコミュニケーションのハブとして機能すること
基礎研修の受講内容
両立支援コーディネーター基礎研修は、私が受講した令和6年度は計7回開催されました。
各回の定員は750名程度で、抽選で選ばれます。
私は抽選に漏れることなく受講することができました。
3週間の間に動画配信研修を受講し、受講後にWEBライブ講習を受講して終了です。
動画配信研修は合計約7時間、WEBライブ講習は2時間です。
動画配信研修は、3週間の間の好きな時間に受講することができます。
動画は早送りすることはできませんが、一度受講して復習用の動画受講時は早送り再生が可能です。
- 両立支援コーディネーターの必要性とその役割および留意点
- 基本的な医療に関する知識
- 産業保健に関する知識
- 労務管理に関する基本的知識
- 社会資源に関する知識
- 両立支援のためのコミュニケーション技術
- がん経験者による当事者談話
WEBライブ講習は、一つの事例が挙げられて、両立支援の個人ワークを行い、解説を聞くという流れです。
途中、選択式アンケートにすべて回答する必要があります。
受講の感想
動画配信研修に関しては、私自身、これまで心理や社会保険、福祉について勉強してきたこともあって、知識面で言えば、新たな知識が身についた部分は多くなかったですが、各分野1時間程度の動画ですから仕方ありません。
とはいえ、社会保険などをはじめて学ぶ方には勉強になるのではないでしょうか。
WEBライブ研修に関しては、事例から「自分で考えてみる」プロセスがとても役立ちました。
ケースワークで考え、解説を聞くことで、支援に当たってどのような切り口と順番で行えばよいのかが参考になりました。
また、支援を考える上で、すぐに解決策を考えるのではなくて、「どこに(誰に)何を確認するのか?」を考えるという視点が役立ちました。
実際に両立支援することになった場合に、この事例を見返すことで支援ができるような気がしてきました。
両立支援コーディネーター基礎研修を受講して、「今後、治療と働くことを両立したい人がいたら、支援してみたい!」という意識が大きくなりました。
障害年金の申請を支援する社会保険労務士として、治療と仕事を両立できるような情報提供まで守備範囲に入れ、より価値のあるサポートを提供していきます。